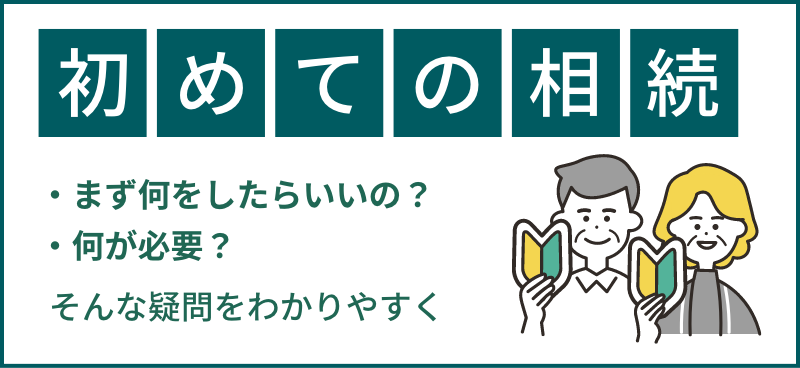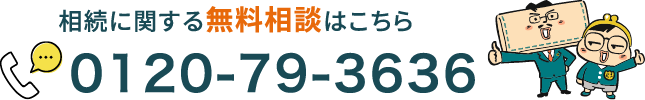相続税の課税方式について解説|法定相続分方式による計算が複雑な理由
世界的にみると相続税の課税方式には遺産課税方式と遺産取得課税方式の二つがあります。
しかしながら、日本の相続税は法定相続分方式といって遺産課税方式と遺産取得課税方式の折衷法が採用されています。
日本の相続税の課税方式がこのような折衷的な方法になった理由に迫ります。
相続税を語る上では、まず民法と相続税法の関係について理解することが必要です。
民法は第一遍から第五編まであり財産法と家族法に分けられます。
財産法は財産取得の一態様として、家族法は遺産の取得資格として相続税法に関係するため相続税法は「社会」「経済」「家族関係」をも考慮して検討されなければならない特殊な税金ということになります。
では、そもそもなぜ相続という考え方があるのか?
相続の根拠は主に以下の三つで語られます。
①遺族の生活保障
②潜在的持分の清算
③権利義務の安定
財産の所有者だった人が亡くなった後でも、その財産を有効活用して家族を守り、かつ、経済が不安定にならないように財産債務の行き先を決めておく必要があるため相続というシステムが存在するんです。
では、なぜ相続税を取られなければならないのか?
相続税の根拠には下記のようなものがあります。
①社会還元説
②社会政策説
③所得税補完説
④財産の無償取得による所得税課税説
⑤偶発的課税説
簡単にまとめると
「財産がたくさんあるところから税金を取って社会サービスにかかる費用に充てよう」
ということです。
そこでどうやって相続税を課税するのか考えられたのが遺産課税方式と遺産取得課税方式です。
遺産課税方式は遺産に対して税金をかけ、残った財産を分割するという方法。
遺産取得課税方式は遺産を分配したあとで、取得額に応じて税金をかけるという方法。
どちらも長所と短所があるため考えられたのが日本が採用している法定相続分方式ということになります。
遺産課税方式と遺産取得課税方式をミックスした折衷法ということになります。
折衷法というくらいですので途中までは遺産課税方式で計算して、最後に遺産取得課税方式の考え方を織り交ぜているイメージです。
法定相続分方式に短所がないわけではないですが、複雑な計算方法になってしまったのにも納得です。
相続税申告や節税対策・遺言書のことなど
お気軽にご相談ください!
この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市出身。
名古屋市と東京虎ノ門の2拠点で活動する相続相談所レクサーの代表。
税理士、行政書士、宅地建物取引士の3つの資格を武器に年間300件以上の相続総合コンサルティングを手掛ける。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
YouTubeで相続の分かりやすい動画を配信中!